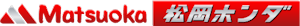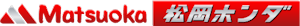店長のブログ :
渦巻き2019-07-19 by 松岡
「人が集まると一人では出来ないことが出来る。」
人が街に集まったり、組織作りに励んだりするのは、このルールがあるから。
魚も同じです。
魚の「ホッケ」は浮き袋が無いのを、ご存知ですか?
あるテレビ番組で他の魚にはある浮き袋がホッケには無いことを学びました。
人間いくつになっても知らないことを知るのは楽しいものですね。
「ホッケ」は、
普段水深100mくらいの所にいますが、春になると群れて渦巻きを作ってプランクトンを周りから集め、仲間にエサを行き渡らせることが出来るそうです。
渦巻きが出来ると、
ある程度の深さまでプランクトンを引き込めるので、カモメに襲われる心配がなくなるのもメリットです。
イワシの群れは丸くボール状になることで敵から逃れます。
BOIDS(ボイド)はアメリカのアニメーションプログラマー、クレイグ・レイノルズが考案・作製した人工生命シュミレーションプログラム。
多数の個体からなる群れの集団運動を、各個体に3つのルールを与えてシュミレーションするアルゴリズムです。
1. 引き離し(近くの個体とぶつからない)
2. 整列(近くの個体と速度と方向を合わせる)
3. 結合(より多くの個体がいる方向へ向かって動く)
3つのルールに従って、CGで生物の動きを再現します。
「ホッケ」の場合、3つのルールだけでは渦巻きが出来なかったので、プラスルールを追加。
1. 海面のエサに向かう。
2. 浮き袋が無いので、一定時間エサを食べたら一旦下に下がる。
これで「ホッケ」が作る渦巻きが出来ました。
一定時間エサを食べたら一旦下に下がるから、仲間皆んながエサを食べられる。
生物学者の2大謎
1. どうやって初めての生命現象が起こったか?
2. 多細胞生物の細胞それぞれの役割はどうやって決まったか?
パプアニューギニアのホタル集団点滅現象はオスの集団求愛現象。
群知能 1+1=3
1. 仲間を見つけたら連結する。
2. 連結したら光を出す。
3. 同じタイミングで光らせる。
自動運転実現へのヒントになる?
生物に当てはまるのであれば、
人間にも当てはまる?
あなたはどう思いますか?

|